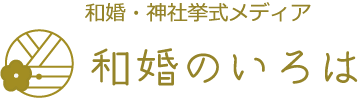神社結婚式において演奏されることの多い、『雅楽』とは?

目次
雅楽の伝来
奈良時代中国、朝鮮半島・南アジアから伝わっております。
平安時代には演奏形式や従来の楽曲が国風に合う形に改められ、専属の楽人を要請する社寺が現れるなど、一般でも演奏されるようになります。
宮中・貴族社会・寺院での継承を経て、他国では廃絶する中で日本独自の音楽として現在に至ります。
雅楽に使われる主な楽器(三管三鼓)
【三管】篳篥(ひちりき)
~地にこだまする人の声~
竹の管で作られた表に七つ、裏側に2つの穴をもつ縦笛。 雅楽の主旋津を担当。

【三管】龍笛(りゅうてき)
~空を舞い立ち昇る龍~
竹の管で作られ7つの指穴をもつ横笛。主旋津に絡みあうように演奏し旋津を豊かにする。

【三管】鳳笙(ほうしょう)
~天からさしこむ光~
翼を立てて休んでいる鳳凰に見立てられる。竜笛・篳篥の旋津に対して和音を奏でる。

【三鼓】鞨鼓(かっこ)

洋楽の指揮者の役割を担い、全体のテンポを決める。
【三鼓】釣太鼓(つりだいこ)

【三鼓】鉦鼓(しょうこ)
金属製の打楽器
雅楽の主な曲目
越殿楽(えてんらく)
雅楽の中で最も有名な曲。古くより親しまれ「黒田節」などに編曲されている。祭事の際に演奏が多
関連記事
-
 和婚のいろは
和婚のいろは神前式の費用は46万〜85万円ほど!内訳を確認して予算を立てよう
神前式を挙げたいとき、どのくらいの費用がかかるのか気になる方も多いですよね。 今回は、神前式にかかる費用相場や内訳をご紹介します。 神前式の費用を抑えるコツもご紹介しているため、コストを抑えたい方はぜ...
-
 和婚のいろは
和婚のいろは【息子・娘の結婚式】親からのご祝儀はいくら?相場や挙げるタイミング、渡し方を解説
「子どもの結婚が決まったけれど、ご祝儀はいつ渡すべき?」「ご祝儀の相場はどれくらいなんだろうか」「結婚式をしない場合のご祝儀の渡し方は?」 お子さんの結婚が決まった際に、このような疑問を持つ方が多いの...
-
 和婚のいろは
和婚のいろは両家顔合わせで輝く、夏のフォーマルファッション攻略法
両家顔合わせは、結婚に向けた重要な儀式の一つです。特に夏季は、暑さや湿度への配慮が必要となり、服装選びに悩む方も多いでしょう。 マナーを守りつつ、おしゃれで涼しげな装いを実現するには、どのようなポイン...
-
 和婚のいろは
和婚のいろは両家食事会を成功させる秘訣!準備から当日まで完全ガイド
結婚を控えたカップルにとって、両家の食事会は大きな山場の一つです。初めて顔を合わせる両家の親族、漂う緊張感…。そんな重要な機会だからこそ、しっかりとした準備が欠かせません。 「でも、何から...